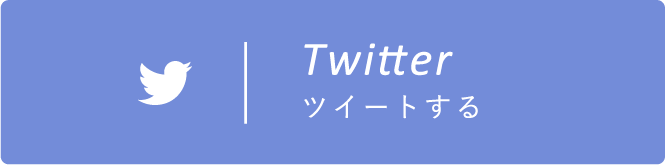岡山県
西粟倉
にしあわくら
「温泉宿があれば、森に関わる人を増やせる」株式会社sonraku・井筒耕平さん。(私と百森vol.11)
Date : 2018.02.13
西粟倉に足を運ぶ人の多くが訪れるゲストハウス、「あわくら温泉 元湯」。
温泉にゆったりと浸かる時間は旅情を誘うが、この地域の源泉は湯温が低く、そのままでは入れない。湯を沸かすためのエネルギーが別に必要なのだ。
「ならば化石燃料ではなく、西粟倉の豊富な資源を使おう」と打ち出したのが、百年の森林構想。元湯の運営を行う井筒耕平さんはこれを受けて、地元の間伐材で薪を作り、温泉施設などに薪ボイラーで熱供給を行っている。
西粟倉に来て3年半。今後は拠点を神戸に移すことも考えているという井筒さんに、これまでの歩みと、現在の思いを聞いた。
バイオマスには可能性がある
– 井筒さんは、同じ岡山県内の美作市から2014年に西粟倉に来られましたけど、生まれは元々どちらなんでしょう?
井筒:生まれは愛知県で、高校卒業までいました。それからスキーをするために北海道に行きたくて、北海道大学の一番偏差値の低い水産学部に進みました。学部への興味は全然無かったんですけどね。
就職は国際物流を行う静岡の会社。港でのオペレーションの仕事をしていました。
– そうした、いわゆる‟海系”から今のように‟山系”にシフトしていったのはどこで?
井筒:国際物流会社を辞めて、なんとなく、ざっくりと環境系を学んでみたくなって、大学院に行ったんです。そこで、先生が「田舎はエネルギーがどんな風に回っているのかが見えやすい」と、中山間地の田舎に連れて行ってくれたのが大きな転機のひとつになりました。バイオマスというものに出会って面白いなあと思ったのもこの頃です。

それと、学校内にいろんな分野で地球の歴史を研究している先生や生徒がいたことも大きかった。たとえば地球の気候変動問題ひとつとっても、温暖化と言われているけれど、長期的には地球は温暖化と寒冷化を繰り返している。だから、「短期的な視野ではなく、長期的な視野で見なければ全体のことはわからない」ということも学びました。
– 俯瞰して見ると、物事がまるで違って見えますもんね。視点を変えることによって理解が進むというか。
井筒:そう。ほかにも長い時間をかけて地形を形成する、大地の隆起や沈降に地球のダイナミズムを感じて、目の前で起きていることや交わされている議論を近視眼的に見るのは良くないなと思ったんですよね。もっと地球規模や、長い歴史の時間軸で見ていかないと本当のことが見えない。
– 「俯瞰の目線を得る経験」は、井筒さんの人格形成にもかなり影響があったんじゃないでしょうか?
井筒:はい。その俯瞰の目線は、大学院卒業後にインターンをした環境エネルギー政策研究所(ISEP)というNGOでも役立ちましたね。そこでは、国際規模のエネルギーに関する政策提言を国会議員さんなどにしていたんですけど、その場合にも、東京でエネルギー政策をやっている人たちと、ローカルの現場で実践を行う人たちの両方を見ていかないと、全体を把握しての提言ができなかったので。
やっぱり大学院が面白くって、「自分は再生可能エネルギーに関することで働いていこう」という気持ちになっていったんですよね。当時はこの分野に取り組む人が今よりも少なかったし、制度面も整備されていなかったし。
– 再生可能エネルギーにも選択肢がたくさんあったと思いますけど、そのときは具体的に何をやっていこうと思っていたんですか?
井筒:やはり、分野でいうと化石燃料に取って代わる資源として、バイオマスに可能性があるかなと思っていました。もちろん太陽光や風力にも可能性はあるけど、ぼくはたまたま中山間地域の田舎に行って、林業とバイオマスに出会っていたので。そこから環境コンサルティングの仕事をするようになっていったというわけです。

西粟倉のバイオマスボイラーの燃料となる薪。
現場のリアルに飛び込みたかった
– 環境コンサルタントから、今では自らが西粟倉でバイオマスを使った地域熱供給のプレイヤー。キャリアとしてはかなり振れ幅がありますよね。
井筒:環境コンサルティングの仕事をしていたときに、地方自治体でエネルギービジョンを掲げた冊子を作ることになって、ぼくはそれをコンサルタントとして書いていたんですよ。でも徐々に、「いくら計画や報告書を書いたところで、実際にやる人がいないと世の中はなにも変わらないんだよな」と感じるようになって。
– いわゆる「プレイヤーいない問題」ですね。
井筒:はい。それと、そうした報告書をたくさん書いていながらも、自分自身で意味がわからないこともたくさんあったんですよ。たとえば、「林業は衰退傾向にある」と自分で書いていても、なんで儲からないのかもわからないし、どうやって売上を立てているのかも、林業をやっている人の気持ちも、具体的なところはよくわからない。実際に自分でやってないので当たり前なんですけど。

ご自身の運営する元湯のカフェスペースにて。
– 現場のリアルがわからない。
井筒:ええ。だから、「プレイヤーいない問題」と、「現場のリアルがわからない気持ち悪さ」というふたつがあって、一度自分がプレイヤー的な立場を経験しないと、この先そうした報告書を書いたり自治体の人たちと議論するにしても、説得力が無いんじゃないかという気持ちになって。
– 環境コンサルタントをしていた会社では、井筒さんの他にもたくさんのコンサルタントが働いていたと思うんですけど、そういった違和感を抱えて実際にプレイヤーになっていく人ってあんまり…。
井筒:いないですよね。もちろん、コンサルは常に最新情報を得ているので、今現在、自分がプレイヤーの立場で彼らと話すとすごく学ぶこともあるし、役割として必要だなと思いますけどね。
ちなみに西粟倉の百年の森林構想との出会いも環境コンサルタントの会社で働いていた頃でした。
美作から西粟倉へ
– 西粟倉の以前にいた美作へは、いつから行かれたんですか?
井筒:美作の上山集落に、地域おこし協力隊として2011年から入りました。山に入ったり、棚田の再生をする人を募集していたんですが、現場に飛び込むいい機会なので自分を鍛えてみようと。
棚田70枚くらいでみんなで米作りもしましたし、春から秋が農業で、秋の後半から冬が林業。ユンボで400mくらいの作業道づくりもしました。‟ザ・現場”でしたね。やってみてすごくよかったことは、チェーンソーや刈払機やユンボとかを使うスキルがついたこと。
ただ、市役所との協働であったり、薪ボイラーを施設などに導入していきたいということについてはなかなか推し進めることができなくて。協力隊の任期が終わった後の未来を上山で描くのが難しいと感じたのも事実でした。
– よくも悪くも、はじめて現場に入ったことで見えてきたことがたくさんあったわけですね。少し遡りますが、環境コンサルタント時代に西粟倉の百年の森林事業を知っていたとのことですが、当時はどんな風に見えてましたか?
井筒:当時は美作市に関わっていたので、西粟倉は隣町だし、心情的にはライバルというか、「負けないぞ」っていう感じだったですかね。
それでも西粟倉のやっていることに興味はあったので、影石小学校のカフェに行ってみたり、牧さんともお会いして話したこともありましたね。ぼくは岡山県の小水力発電推進協議会の事務局もしていたので、そこで上山参事と会ったり、そういう関わりはありました。
– その頃は、やがて西粟倉に来るなんて考えてもいなかったわけですよね。
井筒:はい、全然考えていなかったです。西粟倉に来ると決めたのは2014年の1月。美作での協力隊の任期が2014年の3月までだったので「よし、動こう!」って。

西粟倉村の小水力発電所、めぐみ。
– 任期が終わるとき井筒さんのなかで、ほかにどんな選択肢がありましたか?西粟倉に来る以外の選択もあり得たのかなと思いますが。
井筒:思い切って岡山県を出て、遠くに行くことも考えたんですけどね。でも美作にいたとき、東粟倉で木材を集めて使うための「鬼の搬出プロジェクト」を始めていたり、勝田でも間伐したり作業道をつけたりしていたんですよ。
つまり、西粟倉の東西で現場を持って動いていた。当時住んでいた上山は西粟倉の南側なので、どっちにいくのにも片道一時間くらいかかっていたので、西粟倉に行けばどっちにもアクセスしやすくなるんじゃないかと。
あと、西粟倉には2013年度にコンサルタントの立場でも入っていて「薪ボイラーをやりましょう」という働きかけもしていたんです。役場の上山さんや白籏さんや議員さんたちを高知に視察に連れていったりもして。だから、西粟倉に行ったらいろいろできそうだなという思いもありました。

薪割りの作業を行なっている当時の井筒さん。
– そうした一連の流れがあったんですね。
井筒:ええ、自分は当初西粟倉に行くつもりは全然無かったんですけど、やっぱりコンサルに入っていたことで状況がすでにいろいろ見えていたのは大きかったですね。
西粟倉がいいなと思ったところは、まず、役所の人と話していても話のレベルが高かったこと。それに、ぼく自身に期待されてることのレベルも高くて、成長できるように感じられたこと。だからすごくわくわくしていました。
ちょうどぼくが美作の地域おこし協力隊の任期が終わって卒業する年から、日帰り入浴の黄金泉に薪ボイラーを入れるのが決まっているというのも、すごくタイムリーでしたよね。それも百年の森林事業の一環だったわけですしね。
「温泉」なら興味を持ってもらえる
– 西粟倉に来ると決めて、当初やろうとしていたのは具体的にどんなことでしたか?
井筒:まず、「薪を割る人がいない」と聞いていたので、薪割りはやろうと思っていました。でも、薪割りだけじゃ生活が大変なので、コンサルタント業(自治体向けの報告書書き)も並行してやったら食ってはいけるかなと。
薪割機で薪を割ったら黄金泉が買ってくれるというのはわかっていたので、その部分ではお金の計算も出来ていて。

薪割り機を使った薪割り作業。
– 実際に西粟倉に来てみて、いかがでしたか?
井筒:理解者も多くて、めちゃくちゃ動きやすかったです。
黄金泉の次に元湯に薪ボイラーを入れるというのも決まってたんですけど、西粟倉に来てすぐの2014年の6月くらいには、ぼくが元湯の運営をするっていうことを村長と話し合い始めたくらいで。
元湯に関しては、薪ボイラーを自分で運用してみたいなという思いもあったんですよね。なぜなら、一般の人に「バイオマス」と言っても興味を持ってもらえないけど、「温泉」なら興味を持ってもらえるから。お客さんを迎え入れながら「ここ、薪ボイラーというものを使っているんですよ」って言えるし、わかりやすいですよね。

リニューアルオープンした元湯の温泉は、村内外の憩いの場。
村にもしっかりプレゼンしに行って、「村は赤字補てんをしない。完全に独立事業でやる」ということでぼくが元湯をやることになりました。
やると決めたのは2014年9月くらいだから、薪割りを始めるのとほぼ同時くらいにどうやって動いていこうかと考えて、そこから元湯の改装をはじめて、オープンは2015年の4月。怒涛でしたね。最初の従業員集めも大変でした。
– 元湯を始めるに伴って、建物も改修する、人も集める、ボイラーの運用や収支も考えなきゃいけない。やらなくてはいけないことが目白押しだったと思いますが、精神的にはどんな状態でしたか?
井筒:全然平気でしたね。ハイになっていたのかもしれないです。むしろ元湯よりも大変だったのは薪割りの方で、黄金泉で朝6時から薪ボイラーに薪を入れても温泉の温度が上がり切らず、営業時間の朝10時に間に合わなくて怒られて、へこんだり…。あと、雇っているスタッフが辞める時もへこみますね。
– 井筒さんが人を雇用し始めたのも、西粟倉が初めてですもんね。
井筒:そう。やっぱり人間が一番難しいです。
経済効果と雇用を生む、地域熱供給
– 井筒さんのこれまでの歩みを振り返ると、やっぱり西粟倉での3年間が一番自分の思いのままに‟走れた”という印象ですか?
井筒:以前はぬかるんでいて走りたいけど走れなかったけど、西粟倉は加速がついて走れちゃった、って感じですかね。今は、2016年の最後にあわくら荘にも薪ボイラーが入って、それで一旦やりきったというか、気持ちの上でやっとひと段落ついたというところです。
…まあ、俯瞰して見ちゃうんで、西粟倉だけじゃなく、いろいろやるべきことや場所はまだ他にもあるだろうなとは思っていますかね。

元湯ではオリジナルのお土産も販売。
– 井筒さんは、現在も元湯の運営や薪割りの仕事と並行して環境コンサルタントとして各地を回っていますけど、「西粟倉だけじゃない」というのは、やはりバイオマスによる熱供給がそれぞれの地域でそれぞれの形で増えていったらいいな、という思いですか?
井筒:そうですね。そういう真面目な思いと、人生一回しか無いからいろんな場所を見てみたいっていう純粋な好奇心もありますね。
あと、「西粟倉だから、バイオマスによる熱供給ができるんでしょ」って言われることも多いので、「そうじゃない」ってことを示したいというのもあります。そう言われてしまうことに悔しさもあるし。
– そもそも西粟倉に来るときにやろうとしたことを、もう大体やれちゃったという実感もあるんでしょうか。
井筒:もともとはバイオマスをできればと考えていたわけですけど、今は元湯で薪ボイラーの運用もやっていて、やりたかったこと以上のことができてしまったという感覚はありますね。
なので、子どもも来年から小学生になるし、一旦ちょっとひと段落というか。西粟倉の前から全部含めて岡山県の田舎に12年。もう岡山に対しても全然俯瞰して見れていないと思うし。
今は都市の問題が新鮮に見えるし、都市に行けばまた西粟倉が新鮮に見えるんじゃないかとも感じていて。…というわけで2018年4月から神戸に引っ越すんです。神戸空港を使えば日帰りで出張もできるし。もめさん(元奥様)の実家が神戸で子どもを見てもらえるというのもあって。

村内のローカルベンチャーのアイテムも充実。
– そういうことだったんですね。では、改めて、西粟倉で過ごした3年は、井筒さんにとってどんなものでしたか?
井筒:うん、ほんっとうにいろんなことを実現できて、超楽しかったです。今も充実していますし。会社を動かすことを含めて現場のいろんなリアリティも勉強になりました。
あらゆることが本当に自分の力だけでは絶対にできなかったことで、西粟倉に来たことで百森がぼくを走らせてくれた。西粟倉の役所もそうだし、民間企業のみなさんも。本当に相乗効果っていうんですかね。牧さん経由でいろんな分野の人たちと繋がることもできました。
– 数字に見える経済効果もけっこうありましたよね。
井筒:今は年間売上が5800万円。実際、売上は宿業が一番良くて、コンサル、バイオマスの順です。
バイオマスの仕入れは百森で、作った薪を、黄金泉などを手掛けている「あわくらグリーンリゾート」に燃料代として買ってもらっています。ただ、人件費と仕入で売上の9割くらいが出ていくので、利益を出すのは難しいですが。
買う側からすれば今は灯油よりも少し安いくらいですね。バイオマスは価格が固定で、価格決定権が自分に無いのが経営としてはきついところ。でも、西粟倉に視察に来てくださるお客さんが元湯に泊まってくれたりすることも多いので、営業効果があると考えればまあなんとかいいかなと。でも本当に元湯をはじめて良かったですね。
雇用を生んだってことに関しても結構貢献できたかなと思います。今はスタッフは元湯の方でパートも合わせて17人。薪工場では薪を作って運んで、投入する人が4人です。

村内の温泉施設に導入されている薪ボイラー。
兼業林家を増やす、寛容な百年の森事業に
– 西粟倉の3年で、つらかったことなどはありましたか?
井筒:…なんでしょうねえ。まあ今はまだ全般的に村の中でバイオマス事業がそれほど知られていないと思うので、一般家庭に薪ボイラーや薪ストーブを広げていけたらいいなあと思いますね。
– すごいですね。ぼくは今「つらかったこと」を聞いたんですけど、つらかったことではなく、これからの事が出てくるというのが。西粟倉での充実を改めて感じます。
井筒:ま、忘却力があるので(笑)
– 忘却力があればこそ、「次」に進む力になるのかもしれないですね。百年の森林構想は2058年を見据えていますが、その頃、西粟倉はどうなっていたらいいなと思いますか?
井筒:いろんな林業のやり方をする人が増えていたらいいなと思います。もっと気軽に、いろんな年代の人に、森に関わる兼業林家になってほしい。そのためには、もっと寛容な百年の森林事業になるといいのかなとぼくは思っています。
どういうことかと言うと、今は村外からも原木を仕入れていて、もっと村内の木を使わないといけないという現状なので、西粟倉の森から搬出する原木の「量」を増やすことがミッションになっているんです。でも、量以外のもの、たとえば「森に関わって働く人の数」を指標にするといったことです。
そうやって寛容になると、異分野の人が入ってきやすくなるし、結果としてイノベーションが起こりやすくなるから。その寛容さのさきがけに、村落エナジーがなってみようかな。「冬しか林業をやりません」とかね(笑)。

元湯での取材は、終始穏やかなムードでおこなわれた。
– 農家がオフシーズンの冬場に、酒蔵に入って蔵人になるようなイメージですね。
井筒:そうそう!昔、昭和30年代に45万人くらい林業家がいたころは、みんな「農家林家」だったりしたわけで、兼業林家だらけだったんです。それが今では林業家はほとんど専業になって4.5万人しかいなくなってしまったんです。
– 農業だと、生産効率の向上に伴って一人当たりの生産力が上がっているので、農家の総数が減っても潜在的な部分も含めてトータルの生産力自体は落ちていない。林業はその点ではいかがでしょう?
井筒:林業も、人が減ってるからすごいハイテクマシンを入れる方向なんですよね。でもハイテクマシンはすごくお金がかかるので、投資を回収するためにマシンを年中動かす必要がある。そうすると専業になっていかざるを得ない。だからもっと小さくて汎用性のあるユンボを使って、「こんなやりかたでもできる」っていう兼業林家が増えるといいなって。
兼業林家が増えたら、実際に搬出量も増えると思う。雇用も増えるはず。ドイツは46万事業体とかあるんですけど、ほとんどが小規模の個人なんです。合算すると経済効果も大きい。

元湯内に構えるペンギンは、じっと未来を見つめている。
– 多くの人の自分事になることで、社会的で開かれた山になっていくというわけですね。井筒さん自身のこの先、そして2058年はいかがですか?
井筒:80歳台か…。10年後さえ読めないですからね(笑)。
今は、田舎にいることで、いろいろ情報が入ってこないなと思う部分もあるので、感覚として都会のリアリティを知りたいです。
でも、西粟倉にもこれからも週に一回は必ず来ますしね。あと、関西の人って西粟倉のことを全然知らないので、ぼくが神戸にいるだけで西粟倉の営業になるんですよ。そうやってどんどん西粟倉のこともお伝えできると思っています。
– 井筒さんは、全体を俯瞰した研究と、現場での実践を両輪で回しているようなイメージがありますね。
井筒:そうですね。そんな感じです。2058年ということでいうと、もちろん元湯は続いていて、スタッフがどんどん入れ替わりながらも、よりよい場所になっていればいいですね。

素敵なスタッフがいるから、次に進める。
でも、西粟倉に百年の森林構想があって本当によかったと思います。というのも、ほかの自治体にコンサルに行っていてよく感じるのが、立ち返る軸があるのと無いのとでは全然違うなということ。西粟倉には百森構想があるから、なにかあったときに掴まることができるし、立ち返れる。行先を指し示したロードマップであり、マスタープランですよね。なので他のまちにもこうした指針を作ることをオススメしているんです。