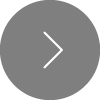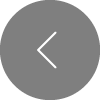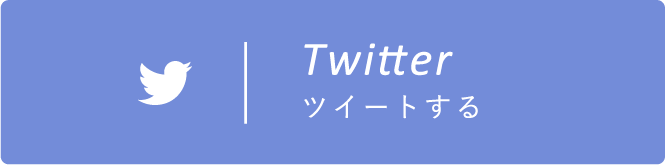岡山県
西粟倉
にしあわくら
「百森」があったから戻れた、母の出身地。 がらんどうの工場から、売り上げ3億円超までの道のり(私と百森Vol.9)
Date : 2018.01.24
「百年の森林構想」の旗振りのもと、西粟倉で動き出したものがたくさんある。たとえば「西粟倉森の学校(以下、森の学校)」は百年の森林構想のエッセンスを体現した会社として誕生したといっても過言ではない。そして、森の学校の働き手として村にやってきた西岡太史さんは、西粟倉で人生を歩む覚悟を決めて、母の故郷にIターンした。
美しい物語とともに産声をあげた森の学校で、働き始めた西岡さん。ただ、理想と現実の間には、その場にいるものだけが知る大きな溝があるものだ。その溝の淵でどうにかふんばり続けて現在7年目、売り上げは3億円を超えるまでに。百森が掲げる美しいストーリーとのギャップに悩みながらも、一歩一歩進んできた現場の声を聞いた。
あきらめていた「西粟倉の仕事」を発見
– もともと西岡さんは西粟倉のご出身なのですか。
西岡:僕の母親が西粟倉の生まれなんです。母は中学校2年の時に父親を亡くしていて、母親と西粟倉を出て兵庫県の姫路で暮らしていました。僕も姫路で生まれ育ったんですが、お墓は西粟倉にあったので、年に1、2回は帰っていました。でも、家はないし、親戚もほぼいないし、ただお墓があるだけという感じでした。
僕は高校を卒業して大阪に出たんです。テレビのセットや展示会のブースを組んだりとか、イベント会場の装飾をする仕事をしていました。ただ、長男だし、お墓もあるし、いつか西粟倉に戻ることになるのかなぁと漠然と考えていました。それが、定年を過ぎてからなのか、どんなタイミングなのかは分からなかったですけどね。
大阪で結婚して、そんな話をしていたので、嫁さんも西粟倉という場所については気になっていたようです。
– 自分が暮らすことになるかもしれないと思うと、気になりますよね。
西岡:そうなんです。だから、森の学校の工場ができて社員を募集しているという告知は、嫁が見つけて来たんですよ。それを見て、「失敗するなら若いうちの方がいいし、行ってみるか」と、森の学校の面接に行かせてもらいました。それが、西粟倉に来るまでの大きな流れです。

これまでの経緯を丁寧に振り返りながら、言葉を紡ぐ西岡さん
– 西粟倉に面接に来たときは、何歳だったんですか。
西岡:7年前、28か29歳くらいかな。結婚して1人目の子どもが1歳と少しくらいでした。西粟倉が、新たに仕事が出てくる場所だとは到底思っていなかったので、求人を知って、これは行ってみなくちゃ、と。
森の学校の代表の牧さんに面接をしていただいたんですが、帰りの車の中でもう「来てください」みたいな電話がかかってきたんです。実は、「なんだこの人、そんなわけないやろ」って思いましたが(笑)、「ありがとうございます」ってとりあえず言って……。
– あまりに早くてどう返事していいか分からないですね(笑)。どんな職種の求人だったんですか。
西岡:忘れちゃいましたね。でも、製造ラインの立ち上げみたいな感じだったはず。「営業職」ってなると抵抗があったかもしれないけれど、つくることに関しては、全くの畑違いというわけではないな、と。7月の半ばくらいに面接をして、10月1日から働き始めました。工場長含め、同日入社の人が集まっていました。その前後で、かなりの人数が立て続けにスターティングメンバーとして入社していたようです。
工場はある、仕事はない、五里霧中のスタート
– 小さい子どもも連れての家族で引っ越し、大変そうですよね。
西岡:大変でした。大変なことしかなかったんじゃないですかね(笑)。まず、僕の仕事の都合をつけるのが大変でした。前職の秋の繁忙期に重なっていたので、9月30日の夜23時くらいまで現場で働いて、10月1日にはここで働いていましたから。とりあえず身体ひとつで来て、引っ越しの段取りは嫁さんにお願いしました。10日後くらいに家族もやってきました。
– はじめの仕事はどんなことをしたんですか。
西岡:うーん、なかったいうか……。工場でつくるものも明確に決まっていない状況で、その工場をつくりましょう、という段階。びっくりしました。
– 恐怖ですね。つくるものは決まってないのに工場はある。
西岡:しかも、人はどんどん来る。本当に驚きました。そんなこと、世の中にないと思っていたから。10月1日に村の案内をしてもらって、次の日から基本的にやることがなかった。この状況を理解するのにしばらくかかりました。

当時の様子は、今の製材所からは想像もできない
– しばらくってどれくらいですか。
西岡:2、3週間かかったんじゃないですかね。正直、牧さんに騙された!みたいな感じだった。その時はまだ「牧さん」でもなくて、「あの人」くらいだったから、「なんかあの人に騙されたなあ」って。
製造ラインをつくり上げていくところからのスタート要員だと思ってやって来たけれど、どんな準備がされているのか、僕も聞いてはいなかった。バカでしたねえ。
でも、一大決心できているわけですから、「騙されちゃってねえ」って家族に言うわけもいかなかったです。
– 会社ではそんな状況で、家ではどんな風にふるまっていたんですか。
西岡:自分が理解できていないのに説明もできないので、基本的には普通にしていました。家族を勝手に連れてきたのに、自分のストレスばっかり言うわけにもいかないです。もちろん、会社としても実際は騙すつもりだったんじゃなくて、予定していた取引先が急になくなったりして大変だったんですよね。
– なるほど。ぐっと自分のなかに押しとどめて、すごいです。会社ではじめて仕事らしい仕事をしたときのことは、覚えていますか。
西岡:入社して3日目くらいですかね、やることがなかったので「休憩所でもつくるか」とスタッフの人が休憩できる場所をまずはつくりましたね。前職でやってたことをコツコツやった感じです。
その後は、牧さんから「こういうのを欲しがっているとこがあるよ」って言われて試作を繰り返しました。夏休みの自由研究みたいな話ですよ。手探り感がすごかった。あの頃、「木が反ると書いて板だもんな。すげーなー」って思ったのを覚えています(笑)。

– あぁ、そうか!考えたこともなかったです。
西岡:それまで仕事でつくっていた大道具は、期限がくれば壊します。恒久的なものづくりとはギャップがあって、その壁は自分自身の中で大きかったです。
そうこうするうちに3ヶ月くらい経ってやっと、工場で木材加工するにあたって必要な設備を、選定したり調査したりする役割をやらせてもらうことになりました。明確な役割としては、それが最初の仕事だった気がします。
– 設備を選ぶのは、だいぶ重大な役目ですね。
西岡:これも最初は手探りで、パソコンで「せいざいき」って最初ひらがなで検索しましたから(笑)。ただ、良い条件を引き出して、得する買い物をするのが好きな気質があって、この役目を買って出たんです。
製材機を買うのにも、いろいろなところに視察にも行かせていただいて、メーカーさんとも交渉をしながら仕様を決めて、森の学校では中古で2000万円切るくらいのものを導入しました。
そのあとも工場の機械の選定には関わっていますが、スタッフが疲れにくくなったり、ケガをしないような設計にしたり、いろいろ工夫しているんですよ。

パートさんが使いやすく、怪我をしないように設計した台車
「騙されただけ」は嫌。ここにいる理由を自分でつくる。
– 西岡さん自身のターニングポイントについてもお聞きしたいです。仕事はずっと苦しい状況でしたよね。どこか浮上したポイントなどあったでしょうか。
西岡:そうですね、長い間、そんなに楽しくなかったです(笑)。2〜3年の間、全然楽しくない時と、そんなに楽しくない時とウロウロしていた感じですかね。
– けっこう辛いなか、頑張ってた。
西岡:うーん、辛いっていうほどどん底にいたわけじゃないし、不安を抱えながらもがいていました。
はじめ騙されたぞって思っていたけど、僕は家族連れてきてるんで、会社がダメになるとしても、20人くらいいたスタッフが最後の3人になるくらいまでは踏ん張らないと、家族には申し訳が立たないぞと思っていました。
騙されたとは言いつつ、僕はそこに居続けたわけでしょ。そうすると、時間が経つにつれて半分は自分のせいになってくるじゃないですか。3年くらいかけて自分でもなにかやらなくちゃ、という気持ちに変化していきました。
– 西岡さんがそういう境地になった頃、会社はどんな状態でしたか。
西岡:2013年、次男が生まれた頃なんですよね。
ユカハリタイルをつくり始めたのが2011年で、被災地支援の一環として寄付としてある程度の数量納めさせていただきながら、完成度をあげて商品を育てて、一般ユーザー向けにも売り出していました。ユカハリタイルを量産するための機械を、機械屋さんと一緒につくってもいました。
最初は、タイルもわりばしも、つくったけど売り先がなかったのですが、東日本大震災の支援物資として使い道ができて、そこから道がひらいていきました。
– どれくらいの量の物資を送ったんですか。
西岡:ユカハリタイルは100箱くらい、わりばしは数万膳くらいでした。使っていただくことで商品が変貌を遂げていきました。

森の学校の飛躍のきっかけとなったユカハリ
小売業から流通業。森の学校の変化と成長
西岡:2013年頃から、機械設備を担当しながら、外部の協力会社さんをつくって、取引を始めていました。ユカハリタイルをつくるのに、ダンボールは?接着剤は?と木材以外の調達など、自分たちでやりきれない部分が出てきたんです。外部交渉は僕がやらせてもらう流れになっていたので、現場からは離れていきました。営業と現場の橋渡しのような役割に変わっていきました。
あとは、2012年くらいから原材料の丸太の調達に関わり始めました。それまでは外部の方に調達してもらったり、森林組合の土場に出てきたものを良し悪し関係なく、どんどん入れたりして、わりと雑なことをやっていたんです。まだ、何をつくるかが不明確なうちはそれでもよかったけれど、つくるものが明確だと材料もちゃんと選びたくなります。だから、自分たちで市場の競りで購入して、ちゃんと選ぶようになりました。
同時に、自分たちがつくれないものについてお客さんから要望をもらうことが、どんどん多くなってきたんです。木の材料を使って、外で加工して、販売する場面が結構増えてきたんですね。
– ユカハリタイルとか、床材とか森の学校にあるイメージって、私のなかでは完全にBtoCになっているんですが、どうやら違うようですね。
西岡:圧倒的にB to Bの会社で、売り上げの8割を占めます。一般のお客さんの売り上げは2割に満たないくらいかな。
製材工場って、今二極化しているんですよ。家族経営の小規模の仕上げの会社と巨大工場と。融通がきく中規模の製材屋さんが、今どんどん減っていっているんです。そんななかで森の学校は、「木材のことであれば、全部供給をできますよ」っていう中間を目指しています。
村が今つくっている子ども園も、材料の手配一式はうちでやっているんですよ。西粟倉から出てくる丸太を加工して、仕上げできるものは仕上げして、大きい柱は協力会社にお願いして。

森の学校は中規模の製材業としてのポジション確立を目指す
– とすると、「森の学校」の主なお客さんっていうのは……
西岡:売り上げで行くと工務店さんが多いですね。あとは、大手ゼネコンさんや自治体関係です。
もともと「森の学校」は、西粟倉の山、森にどれだけ価値をつけていけるかを目的としてできたと、僕は思っているんです。
ただ、大きな目標はあるけれど、木材業で生き残っていく試行錯誤のなかで、ユカハリタイルに代表されるような内装に特化して、ぎゅうっと可能性が絞られてしまっていた部分もあった。ただそこで踏ん張ったおかげで、地盤が整えられて、いまからようやく本来の森の学校としてあるべき「流通」の仕事が広がっているんじゃないかなって。そこに、大きな役割があるはず。
森の学校が使う使わないに関わらず、西粟倉から出たものが、いろんなところで、用途にあったものに変わっていくような事業が使命だと思うんです。

– 私が3年前くらいに森の学校を取材した時は、また違う状況だった気がします。そんなに「流通」っていうキーワードを聞かなかった気がします。
西岡:そこに価値があることは、事業を展開していくなかで発見していった感覚があります。さっき言ったこども園は、「この山はこういうものが出るんで、こういう製材をしましょうね」と、山の現場の段取り、コーディネートからやっているんですよね。僕たちは今までの仕事の流れの中で、当たり前にやってはいましたけど、特にこのこども園の仕事を通して、価値があることを強く感じています。
去年、工務店さんからも、「じいちゃんの山の木で息子の家を建てる」みたいな要望がありました。それが完成したらまた、「自分の家の山で家を建てたい」って同じ工務店さんから依頼があったんです。昔は当たり前にやっていたようなことが、全くできなくなっている。でも森の学校ならそれができるとなると、それはプライスレス。費用はそれなりにかかるんですけど、それ以上の価値を感じて、お客様になってくれる方たちがいらっしゃるんです。
– いまのお仕事の話を聞いていると、なりより西岡さん自身が、楽しそうに仕事しているように見えます。
西岡:それはねえ、ものすごく変化してますよ(笑)。しっかり利益も出せる状態にやっとなってきたのも大きいです。林業や木材生産業が元気がないといわれるなかで、自分たちが上向いてきた姿を見せたい。それは結構なモチベーションなんです。
「森の学校って元気でやってんな」、「あの規模で何やって収益上げてんだ?」みたいに、業界の中で噂されたいです。
– そういうモチベーションが持てるようになったのは、いつ頃からですか。
西岡:2、3年前からでしょうか。はじめは市場に丸太を買いに行っても、「お前らんとこすぐ潰れるんだろ?」「あまちゃんが何しに来たんだ」「お前に買わせる木はねえよ」って感じでした。だんだんそれが認められてきて、今では当たり前にやり取りできるようになってきた。
同じように競争して買い付けに来る人たちが取引先でもあるので、同じ木を競り合わなくても、「うちの木を挽いてくれるんだったらお願いします。じゃあこっちの丸太はうちがもらいますから」みたいなやり取りができるようにもなりました。

丸太の流通は、森の学校の存在を物語る重要なファクトの一つ
– まさに流通しているんですね。
西岡:そうですね。毎月リピートしている取引先が30軒くらいはありますから。
– 世間で定着している森の学校のイメージと、今やっていることは随分違う気がします。
西岡:そうですね。BtoCとBtoB、両輪がしっかりあるのが森の学校の真価なんだと思います。BtoBの部分が充実してきて、いいかたちになってきたと思っています。
夢と実務と百森の未来
– 西岡さんにとっての、百年の森林構想って何なんしょうか。
西岡:美しい百森のストーリーを聞いて、西粟倉に来ました。でも、いざ現場で携わると「全然違うじゃん」と、距離がだいぶありました。
素晴らしい事例として視察もたくさん来ましたが、実情が伴っていないと感じていたから苦しかった。森の学校がいろんなメディアに取り上げられるけれど、工場は全然何もできていない。次に新聞になんて出るんだ、テレビになんて言われるんだ、って怯えていました。
僕の実務と百森をつなげてコメントしようとしても、正直全然言葉が出てこないですね。ただ、百森がないと僕は西粟倉に帰ってきていない。そういう意味では、僕の人生の中ではかなり大きなものですよね。

西岡さんと百森をつなぐ象徴である丸太の前で
– 最後の質問です。百年の森林構想の到達点である2058年。西岡さんは77歳ですが、西粟倉の森はどんな風になっているでしょうか。
西岡:40年後も、たぶん山はあると思うんです。どれくらい世の中が最先端になっているかわかんないですけど、なんらかのかたちで山に入る人たちがそれなりにおられて。
今みたいに平均年齢60歳、70歳のおじいちゃんが山に入っていてもいいし、ガシャンガシャンってトランスフォーマーみたいなんが、木を伐っているかもしれない。運用がされていれば、かたちはなんでもいいんじゃないですかね。アナログでもハイテクでも、人が入り続けていれば。
人数は少ないとしても「よりよい資源にならないかな」って山について考える人たちが、西粟倉にいれば、百年の森林構想は続いていくのだと思います。