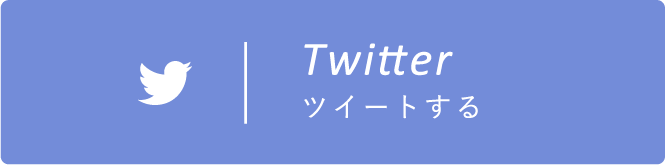岡山県
西粟倉
にしあわくら
ビジネスを通じて地域の新しい未来をつくるための、村民の「願い」調査プロジェクト。みんなが「西粟倉村がよくなればいいな」と願っている調査結果が!
Date : 2023.03.09
村の中にある「願い」を集め、外部のプロデューサーやプロボノ・インターンなどと協働してビジネスへと育てていく「TAKIBIプログラム」。
プログラムを進めるなかで、村民に「願い」をたずねる本格的な調査の必要性が生じ、2023年度から調査が始まることになりました。その結果をふまえ、時間をかけて、「願い」をビジネスへと育てていきます。
その前に予備調査として、2022年秋からパイロット調査が始まりました。実際に村民に会ってお話を聞き取り、それぞれの「願い」を集める調査です。
調査を担当したのは、行政学や地方自治論を専門とする、環太平洋大学の経済経営学部現代経営学科の講師であり、『東京大学未来ビジョン研究センター』のライフスタイルデザイン研究ユニットの客員研究員でもある白取耕一郎さん。
白取さんに、パイロット調査やその結果、今後などについてお聞きしました。
「願い」とは「自分の心身にとって違和感がない、強い希望」
— 「願い」を発掘して実現するまでのプロセスの中で、はじめにお聞きしたいのは「願い」のことです。白取さんにとって「願い」とは何でしょうか?
白取:「願い」とは、いろいろな意味がありますが、私は「自分の心身にとって違和感がない、強い希望」と定義しています。建前で「これがしたい」と言ったり、思いつきで言ったりするものではなく、その人が本当に願っている、違和感のない希望です。なぜかと言うと、表面的な「願い」が叶ってもその人にとって意味がないからです。
もう一つ重要なのは、「願い」は単にニーズに置き換えられるものではなく、その人の持っているお知恵と結びついていること。「こうやったら叶うよな」と思うからこそ、願うことができます。
私はこれまでインタビューを数多く行ってきましたが、地域をこうしたいという「願い」について直接聞いた経験はありませんでした。今回は地域に住む幅広い人の「願い」で、偏りがなく、かつ本音に近いものを集めるのが目的です。どこに「譲れないポイント」があるか、自覚していないかもしれないので、難易度は高いですよね。
「TAKIBIプログラム」では実現するまでのプロセスが4つのステップに分かれています。「①地域の願いを集める、②願いをビジネスアイデアに変える、③アイデアをプランにする、④事業化する」です。今回は①のステップとして、私が医療・福祉に関するパイロット調査を担当しました。これは2023年春から行う予定の本調査の、前段階となるものです。
— パイロット調査は、どのように進めていったのですか?
白取:スノーボールサンプリングという手法を用いました。この手法を使ったのは初めてでした。簡単に言うと、「笑っていいとも形式」でお友達を紹介していただくんです(笑)。すると、幅広い層やこれまで声をあげなかった人にもリーチできる可能性が出てきます。
2022年11〜12月にかけて、10名の調査を実施しました。はじめに青木秀樹村長にお聞きして、3名を紹介してもらいました。その3名に、次の方を1名ずつ紹介してもらい、計7名に。その3名が1名ずつ紹介してくれて、性別や年齢などの異なる計10名になりました。
経験や理論、テクニックなどを使い試行錯誤しながらのスタートで、最後は人間と人間の真剣勝負だと思っていました。緊張感もありましたが、やりがいがありますね。
質問項目は、「第6次西粟倉村総合振興計画」及び村民アンケートを参考にして考えました。聞き取りの際には、地図や資料など十分な準備をしてイメージを一緒にふくらませたなかで聞く、真摯な対話のなかで聞く、「願いが叶うかもしれない」と思っていただける状況で聞く、という3つのことを心がけました。

調査で使用した聞き取り調査用のマップ
研究がとても楽しくて、行政学の研究者に
— 調査の結果を聞く前に、白取さんご自身のこともお聞きできればと思います。東京大学法学部を卒業した後、同大学の大学院に進んでいますよね。
白取:はい。大学院で公共政策学を学んでいたときには、公務員になろうと思っていました。でも、研究の道に出会い、それがとても楽しくて惹かれました。社会問題って複雑ですから、公務員とは違う立場で携わりたいと考えて、行政学の研究者になったんです。
同大学の大学院法学政治学研究科にて博士号を取得しました。博士論文は、政策が波及したりしなかったりすることをテーマにしたものです。博士号を取る前は、『一般財団法人行政管理研究センター』や『東京大学未来ビジョン研究センター』で仕事をしながら研究していました。
現在は、生活保護ケースワーカーの職務上のストレスを研究したり、日本の公的支援制度の受給要件が複雑なので、簡単に検索できるシステムを開発するとともに、貧困に陥っても命を守れるように適切に行動できるようにする「防窮訓練プログラム」を開発したりしています。また、2021年4月から環太平洋大学で講師をしています。
— 「TAKIBIプログラム」に関わることになった背景は?
白取:以前から西粟倉村のことは知っていましたが、私が今も所属している『東京大学未来ビジョン研究センター』のライフスタイルデザイン研究ユニットの客員准教授である関谷剛先生が西粟倉村に関わっていて、「西粟倉村の公共政策は白取先生と合うと思う」とご縁を結んでくださったんです。
2022年6月に西粟倉村の方たちとオンラインミーティングをし、8月から西粟倉村へ通い始めました。村の印象は、山や森はもちろん美しいのですが、住んでいる方々と、その方がもっているお知恵が村の宝だということです。詳しくは後ほどお話しさせてください。

先生が村民と交流している様子
みなさんが「西粟倉村がよくなればいいな」と願っている
— パイロット調査の結果はいかがでしたか。
白取:予想していた以上に、いろいろなお話が聞けました。おおまかな内容だけのご紹介にはなりますが、例えば、「村外の病院にかかることが多いが、どこの病院にかかればいいか分からず、行ってから違うとなれば大変なので、最初にアクセスする窓口がほしい」などの声です。オンライン診療などに期待している方もいらっしゃいました。
また、Uターンの見込みのある人に効果的にアプローチできる方法や、広く情報を届けて納得してもらうことにつながるようなものなども教えていただき、合計で40を超える「願い」を集めることができました。
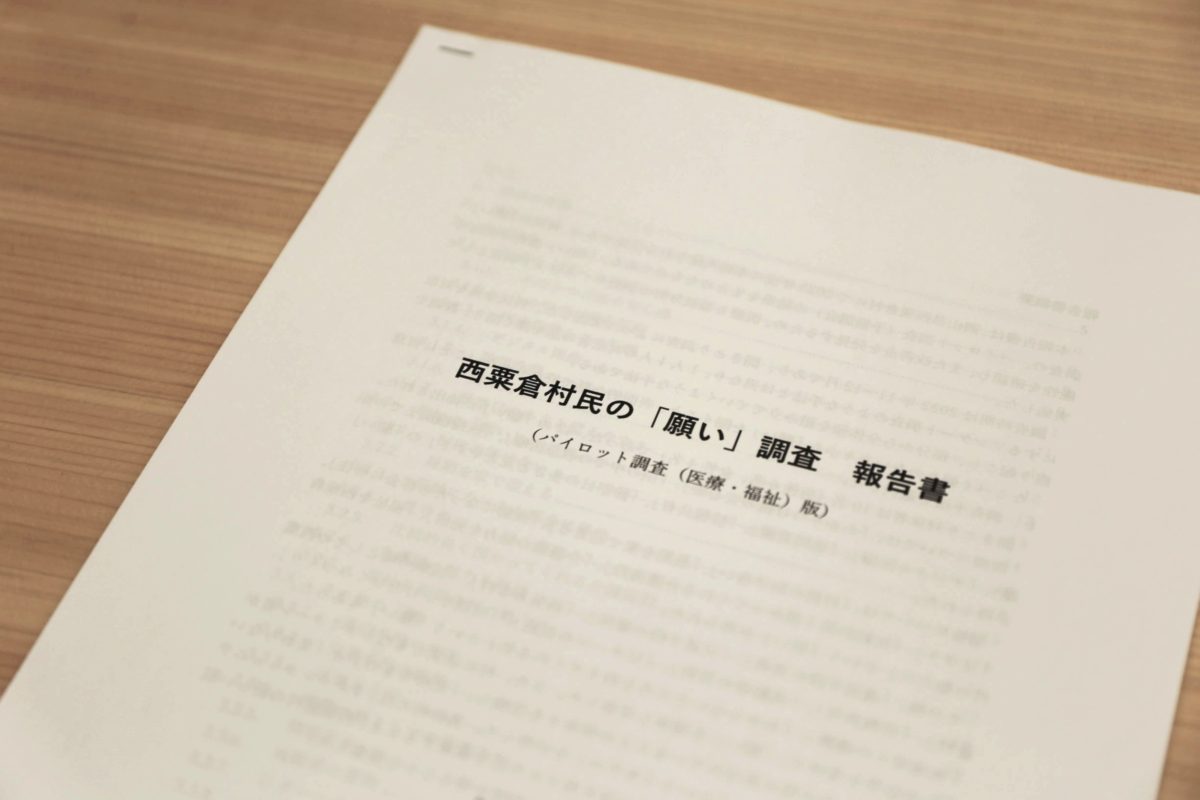
白取氏が作成したインタビュー調査の報告書
— 初対面でそこまで聞けるのは、すごいことですね。
白取:最初は「願いなんてないです」とおっしゃる方が多いんです。ただ質問するだけでは簡単に「願い」にたどりつけません…。90分お話しするなかで、私自身のことを話すなどして、信頼関係を築くよう心がけました。
一緒に飲み物を飲んだりして話していると、ポロッと思いが出てくることがあるんです。最後にレコーダーを止める直前や、または止めた後で「実はこうなんです」と話してくださる方もいて、通りいっぺんの方法では難しいなと感じましたね。インタビューの後にご自宅へ招き、村の未来について語ってくれた方もいらっしゃいました。
印象的だったのは、数名から「村に移住者はけっこういらっしゃるけど、どういう人で何をしているかは直接知りません。でも空き家だったところに灯りがついただけで嬉しく、ありがたいと思っているんです」といったような話を聞いたことです。どんな方かお互いに知れたら、地域がより発展する形になるだろうなと思いました。
そして、みなさんが「西粟倉村がよくなればいいな」と願っていらっしゃると分かりました。それなのに、何かすれ違いがあって一緒にいるのが楽しくなくなったらもったいないですよね。単純に情報を発信するだけでなく、移住者と以前から地域に住んでいる人をうまくつないでいくことが大切になるのではないでしょうか。

一人目に調査を行った青木秀樹村長の聞き取り調査の様子
— うまくつないでいく。
白取:はい、どう出会うかが大事です。道でただ出会えばいいかというと違うんですよね。どのように人と人をつなぐかは、繊細な話だと思います。移住者と地域の人が分かり合うのは簡単ではないかもしれませんが、西粟倉村にはチャンスがあると思っています。
なぜなら、地域の人が「移住者と一緒にいても嫌ではない」と思っている様子を受け取ったからです。知っていてお互いに嫌ではないという状況は重要です。以前から地域に住んでいる人は、Iターンして村でビジネスをしている人のことはよく分からないけれど、攻撃したりはしない。懐の広い方々だと思いますし、それこそが村の財産なのではないか、一番の資産だろうと、感銘を受けました。
ビジネスや新しい活動をする人に着目しがちですが、新しいことをしなくても堅実に暮らしている人の知恵も重要です。私はそこに着目したいと、注意をはらっています。
— 今回の調査結果はどうまとめるのですか。
白取:2023年1月に行われた、事業アイデアを検討するワークショップ「TAKIBIキャンプ」で調査結果の報告をしました。「願い」を伝わりやすい形にして、関係者にお届けしたつもりです。情報量が多いので、本質を残してどうまとめていくかが私のチャレンジでした。
調査結果を発表して、「TAKIBIキャンプ」の議論にも参加して、村民の方々の声を、もちろんまだ一部ではあるけれども、しっかり届けられたという手応えはありました。関係者にとって心地よいものばかりではなかったはずですが、「願い」を受け止めての真剣な議論が「TAKIBIキャンプ」でなされました。ただ、だからといってすぐにそれがビジネスで解決されるような簡単なものではないこともわかりました。私自身も含む関係者の本気さが問われていくと思います。
また、今回の調査は論文にもする予定です。社会科学の方法を使って住民の方々の「願い」を見える化し、それを産官学民の協働でかなえていくようなしくみが確立できたら画期的です。さまざまな形で発表することが日本の将来にとって重要になるでしょうし、西粟倉村は他地域に展開するときのモデルにもなるだろうと。自分のキャリアはとりあえず後回しに考えています(笑)。

TAKIBIキャンプにて、調査結果を報告する様子
— 今後、村への関わりを通じて目指したいこと、大切にしたいことはありますか?
白取:緊張感はもちろんありますが、いつも楽しみに西粟倉村へ足を運んでいます。2023年度は、約50名に聞く本調査を行う予定です。最初の5名の対象者から、10回 紹介を繰り返せば50 名になります。一定の条件下で「現在女性が少ないです」といったフィードバックを行い、村民の属性の分布と大きくずれないようにします。
なるべくあらゆる人にとって居心地がよくなるように、調査を通じて少しでも貢献できたらと思っています。いわゆる「活躍している人」とそうでない人が分かれているのは持続的ではありません。どんな人も、人格をもつ人間です。それに対して誠実であることが大切ですので、人や仕事に誠意をもって接していこうと思います。