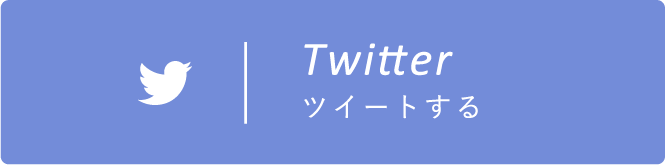新潟県
十日町市
とおかまちし
移住はしない。二つの地元を行き来する 「ダブルローカル」という新たな実験(前編)
Date : 2017.12.08
東京・清澄白河でカフェ&ギャラリー「GARAGE Lounge&Exhibit」、新潟県十日町市ではカフェ&ドミトリー「山ノ家」という二つの拠点で活動するデザインユニット「gift_」の後藤寿和さんと池田史子さん。どちらも“愛すべき地元”として行き来しながら生活し、営みを続ける「ダブルローカル」というライフスタイルを実践しています。もう一つの拠点を持ち、どちらも無理なく継続することは可能なのでしょうか。それによってどんなワーク&ライフスタイルが見えてくるのでしょう。実践者の二人にお話を伺いました。
オープン当初から変わらない“半移住”スタイル
日本有数の豪雪地帯であり、3年に一度開催される「大地の芸術祭」の舞台としても知られる新潟県十日町市松代。このアートが根付いた地域で、古い民家をリノベーションし、2012年夏、カフェとドミトリーが一体となった「山ノ家」がオープンしました。立ち上げたのは、東京にも拠点を持つ空間デザイナーの後藤寿和さんとクリエイティブディレクターの池田史子さん。二人はデザインユニット「gift_」のパートナーであり、夫婦でもあります。

山の家のキッチンに立つ後藤寿和さん(右)、と池田史子さん(左)
この場所を運営しているとはいえ、二人は“移住”してはいません。池田さんは2週間おきに東京と十日町を行き来し、後藤さんは繁忙期やイベントなどがある時にサポートに入り、時には地元のスタッフの助けも得ながら、この場所を切り盛りしているのです。半移住とも言えるこのスタンスは、オープン当初から変わることはありません。

1階のカフェスペース。反対側が一面窓で、通りすがりの人も外から覗くことができる。
「外から見ると変わらないように見えても、じつは考え方やスタイルはどんどん変容しています」という池田さん。自然体でほどよく肩の力が抜けた二人を見ていると、大きな変化もなく淡々とここまでたどり着いたかのように見えます。しかし、二人に話を聞くにつれて、0から1をつくり上げること以上に、継続にはエネルギーが必要だということを思い知らされます。
里山の地で、日常に非日常をつくる
後藤さんと池田さんはもともとデザインカンパニー「IDEE」に所属し、2000 年に始まった東京の街をデザインミュージアム化する「東京デザイナーズブロック」などに黎明期から関わりました。2003年から東京の東側で始まった「Central East Tokyo」でもディレクターとして活動する中で、アーティストやデザイナーがイベント会場となった空き家に移住したり、アトリエをかまえたり、ギャラリーやカフェができていったりと、新たに入ってきた力で街が変容していく様子を目の当たりにしました。「クリエイティブなパワーで変容していく街を体感できたことが、私たちの原体験になっています」と池田さん。日常の中に非日常を生み出すプロジェクトに関わったことが 二人の発想や活動の方向性に大きな影響を与えます。そして、自分たちも「さまざまな人が行き交う開かれた場所をつくりたい」という思いが芽生え始めました。
とはいえ、「その頃はまだ都市にしか興味がなかった」という後藤さん。地方で活動するなど夢にも思っていませんでした。そんな思いを根幹から揺るがしたのが、東日本大震災でした。

「今までギリギリで保っていた部分がめくれていったような感覚になって、このまま東京で今まで通り過ごしていけるのかと考えると、心が揺らぎ始めました」(後藤さん)
このまま東京にしがみついていて本当にいいのだろうか。そんなことを考え始めた震災から3ヶ月後の2011年6月、知人からある相談を持ちかけられました。
「『新潟の里山で地域おこし活動をしている人から、地元で20年使われていない空き家を何とかしてほしいというオファーがあって、お手伝いしてもらえませんか』と。以前なら他人事に捉えていたと思うんですが、この時は地方で何かをやるということを初めて自分ごととして考えることができたんです」(後藤さん)
東京の東側で街の変容に関わり、自分たちも「開かれた場をつくりたい」という思いが芽生えていたところで、東日本大震災によって生き方の価値観が根底から揺らぎ始めた。そこに里山の空き家再生の話が舞い込む、という図られたかのようなタイミングでした。
「数年前なら空間のアドバイスだけをやって、スッと引いたと思うんです。それがいつの間にか自分たちが主体になっていて、ここで起業することになってしまって。当時は誰もやる人がいないならしょうがないね、というノリでしたが、実際には『ノー』と言えるタイミングはいくらでもあった。それでも『ノー』と言わなかったのは、早い段階から“自分たちのプロジェクト”だと思えていたんでしょうね」(池田さん)
外からの新しいパワーによって日常の中に非日常が生まれるという原体験と、東京にいる自分たちが里山の空き家を再生するという話が、二人の中でリンクしたからこそ、これまでにないような可能性を感じたのでしょう。

山ノ家の目の前の松代の通り。外国建築家の事務所兼カフェや地元の店舗なども並ぶ。
十日町に新たな場所を立ち上げても、移住するという選択肢はまったくなかったという二人。それは、里山で生活することが目的ではなく、このご縁を生かして、新たなつながりが生まれるような開かれた場所をつくりたいという思いがあったから。もともとあった街と新しく入ってきたパワーが連携しながら、新しい活力を生んでいく。そんな東京で体感したことを、この十日町でやってみたくなったのです。そこで、空き家を改修して、自分たちのように里山と都市を行き来する仲間を受け入れるための「食べる場所」と「寝る場所」をつくろうと、1階をカフェ、2階を宿屋とすることにしました。
ここで何か大きなことを成し遂げようといった大それた動機があったわけではなく、思いがけない形でのスタートでしたが、その決断の根底には、「都会だけにこだわらない生き方が自分たちの未来をひらいていく」という確信にも似た思いがあったのかもしれません。
アートが根付いた風土が、決断の決め手に
タイミングが合致しただけでなく、この地域の魅力や人との出会いも決断の決め手となりました。その一つが、「大地の芸術祭」がすでに地域に根付いていたことでした。
「風光明媚で食べ物がおいしい。でもそんなところは日本中にいくらでもあると思っていて。やっぱり決め手となったのは『大地の芸術祭』。地元の人たちがこの取り組みを自分ごととして大事にしているのが伝わってきて、ここまで文化プロジェクトを受け入れている土地なら、まったく縁のない土地に飛び込むのとはわけが違うかもしれないと思いました」(池田さん)

地元、越後妻有の明後日新聞社のタブロイド紙のほか、セレクトしたアートやイベントなどのチラシなども置かれている。
そして、もう一つが地元の地域づくりのリーダーでもある、NPO法人越後妻有里山協働機構の代表理事 若井明夫さんとの出会い。二人を自然な形で地元に迎え入れ、プロジェクトを強力にサポートしてくれました。「若井さんとの出会いが、プロジェクトを前に進める原動力になりました」と後藤さんは話します。
「ここは雪深く山手のドン詰まりの場所。それなのにみなさんすごくオープンで、心の扉の開け方が上手なんです。平家の落人などを受け入れてきた歴史もあり、異次元の人たちを迎え入れて共存していく流れが根底にあるのかなと思います」(池田さん)
初開催のツアーで得た、思いがけない収穫
2012年は3年に一度の「大地の芸術祭」の開催年。この時期にあわせてオープンし、スタートダッシュを図ろうと、二人は本格的な準備に動き出します。春から学生インターンを募集し、のべ30人の力を借りて、内装のリノベーションやカフェのメニューの試作などを行い、8月上旬にカフェを、9月中旬にドミトリーをそれぞれオープンしました。

山ノ家のロゴマーク
「宿屋と飲食店どちらも経験がなくて、ど素人だったので、オペレーションもわからなくて。お客さんとして何がないと困るかなと一つひとつ考えながら備品を揃え、1日の流れも自分がお客さんの時はこうだったなとひも解いていったり、ゲストハウスを立ち上げた方からお話を聞いたりしながら、手探りで組み立てていきました」(池田さん)

ふらっと地元の人が寄り道することも。心地よい音楽が流れるカフェスペース。
スタートダッシュは好調でしたが、そんな日も長くは続きませんでした。「大地の芸術祭」の会期が終わると、人通りはパタッとなくなり、土日も誰一人お客さんが来ないという状況に。多少の覚悟はしていたものの、「このままやっていけるのだろうか」という不安ばかりが募りました。
また当時はオペレーションに不慣れだったため、スタッフを雇いながら2〜3人体制でどうにか回していました。この場所を維持するだけでも赤字という状況の中で、当然ながら人件費がかさみます。「3年目までは赤字を積み上げている状態でした」と池田さんは振り返ります。
「スタッフは大事な仲間だったんですが、すべての債務を追うのは経営者の私。自分名義の債務がどんどん膨れ上がっていって、すごく精神的に苦しかったですね」(池田さん)
この状況をどう打開していけばいいのか。そもそも、この地域には外食文化がないので、首都圏からお客さんを呼ばないと始まらない。そこで地元の恩人、若井さんの協力を得て、里山の魅力を味わってもらえるようなミニツアーを企画。11 月の新米の時期にあわせて、地元のキノコ狩り名人と山で採ったキノコでキノコ汁をつくり、羽釜で炊いた新米のごはんと一緒に食べてもらい、里山のアート作品にも触れてもらう。そんなミニツアーを開催することにしたのです。告知は facebook への投稿くらいのものでしたが、想像以上に多くの参加者が全国から集まってくれました。

「真っ青な空と稲刈りの終わった棚田の風景を見ながら、炊きたてのご飯をみんなで食べて。それだけで幸せすぎる!と元気になりました。すごく気持ちがよかったので、こういうイベントってやっぱりいいなと実感しました」(池田さん)
このツアーでは思いがけない収穫もありました。一つは、地元の人に体験の先生をお願いしたことで、地域とのつながりが深まったこと。そしてもう一つは、雑誌「ソトコト」の編集チームが取材を兼ねて参加してくれたことでした。ツアーの様子を誌面で取り上げてもらったことで認知も広がり、運営面でも弾みになりました。

その後は、この地域の気持ちいい時間を共有できる場を季節ごとにつくろうと、春は山菜採り、冬は味噌仕込みなどのイベントを開催。経営的にきびしい時期は続きますが、東京と同じように里山でも生活と生業を行うスタイルを貫きながら、前向きに運営を続けていきます。
日常に非日常が生まれ、変容していく街を目の当たりにしたこと、そして震災によって東京にしがみついていることへの危機感を抱いたことで、地方にもう一つの場所を持つことを選んだ二人。
後編では、二つの場所を行き来する「ダブルローカル」ライフによって、二人の生き方の価値観はどう変わっていったのか、新たなライフスタイル実験を続ける二人の変化に迫っていきます。